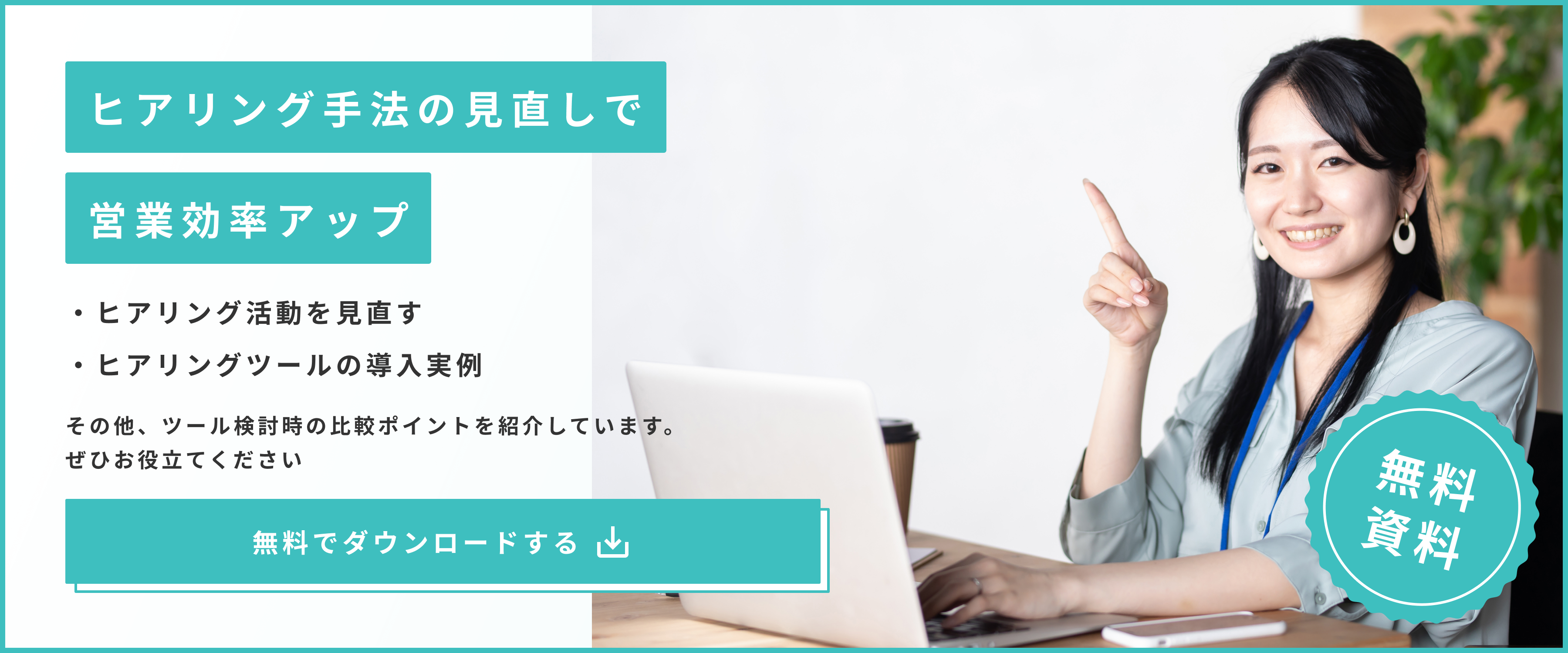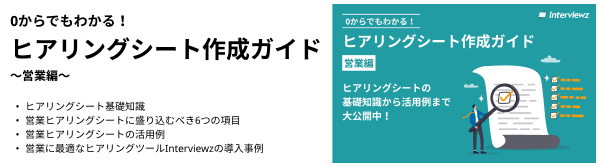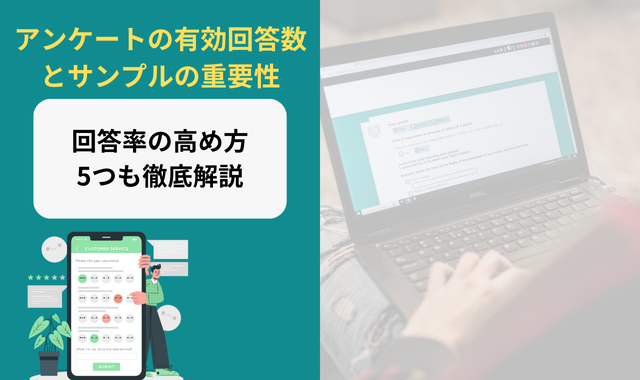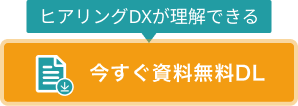Webサイトの直帰率が高い原因4つと効果的な改善方法を徹底解説
- 2022/08/13
- 2025/03/18
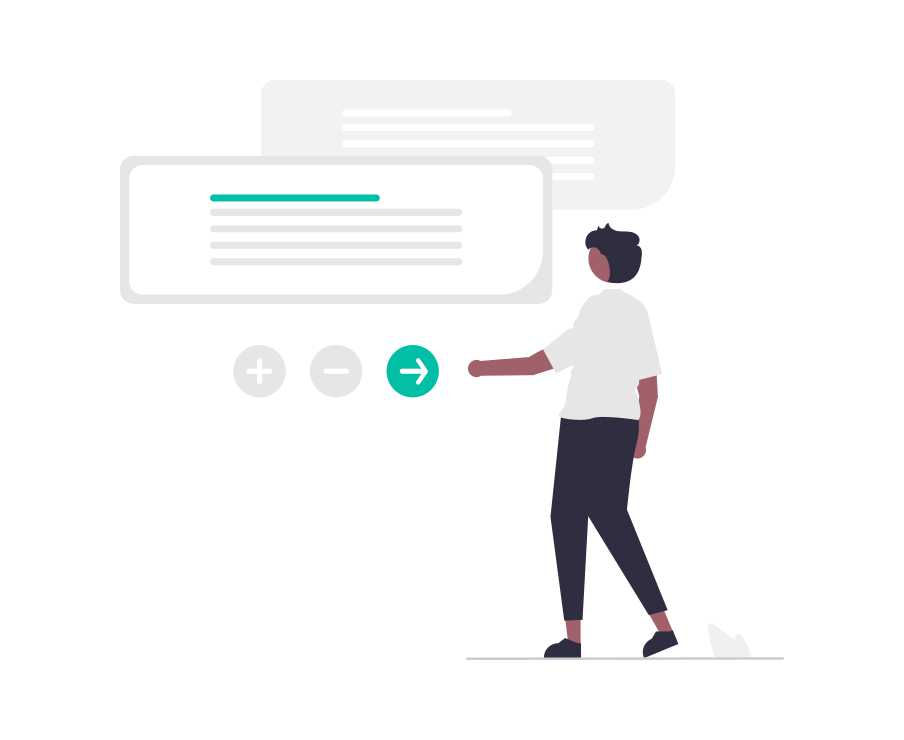
目次
企業がWebサイトを活用したマーケティング施策を成功させるには、訪問者を引き付け、自社のWebサイトに長く滞在してもらうことが重要です。
しかし、Webサイトの運用で最も難しいのが、この直帰率の改善方法にあると言っても過言ではないでしょう。
直帰率とは、ユーザーがサイトに訪れた後、他のページを見ることなくすぐに離脱してしまう割合を指します。この数値が高いということは、サイトが訪問者のニーズや期待に応えられていない可能性が高いということです。
直帰率を改善することで、サイトのパフォーマンスを大幅に向上させることができますが、その原因と対策を正しく理解することが不可欠です。
そこで今回は、Webサイトの直帰率が高い原因4つと効果的な改善方法を徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。
直帰率とは?

直帰率とはウェブサイトに訪れた訪問者が、1ページ目でサイトを去る行動の確率を指します。直帰率が高いということはユーザーが満足できるサイトではないということを意味します。
直帰率はサイトのページやコンテンツ内容がユーザーに適切なものかを判断できる指標と言えるでしょう。
直帰率と離脱率の違い
直帰率と似た意味の言葉で離脱率があります。
直帰率とは訪問した1ページ目から他ページに移行せず直帰したセッションの割合を指します。
一方で離脱率は直帰したかどうかに関わらず、見ていたページを最後に他のサイトへ移行したセッションの割合を指します。ユーザーが閲覧しているページから他のサイトに移動することが離脱となります。
直帰率とはサイトページの1ページ目で他サイトに移動したセッション数の割合のことを指し、離脱率とは対象ページを最後に他のサイトに移動したセッション数の割合を指します。
直帰率の計算方法と目安

直帰率の定義を理解した上で以下では直帰率の計算方法と目安となる業界別の平均について解説します。
現在運用しているサイトの直帰率を割り出し、目安となる属する業界の平均値を確認してみましょう。
直帰率の計算方法
直帰率は直帰したユーザー数をサイトに訪れた全体の数字を割ることで算出可能です。直帰率の計算方法を誤ると、正しいサイト運営ができなくなるため正しい計算方法を理解しましょう。
直帰率の計算方法は以下です。
直帰率=直帰数÷セッション数(訪問数)
例えば、セッション数が1000人に対して直帰数が510人だった場合、直帰率は51%になります。各業界で平均直帰率が異なるため、自社の直帰率が適切かどうか確認が必要です。
510人(直帰数)÷1000人(セッション数)=51%(直帰率)
直帰率の目安となる平均値
直帰率はサイトの運営方法や、ユーザーの属性によっても異なります。
Webサイトの直帰率の目安は、ページの種類によって大きく異なります。以下の表で、主なページ種類ごとの直帰率の目安を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
| ページの種類 | 直帰率の目安 |
|---|---|
| ECサイト | 20〜45% |
| B2Bサイト | 25〜55% |
| リードジェネレーションサイト | 30〜55% |
| コンテンツサイト | 35〜60% |
| ランディングページ | 60〜90% |
| 辞書・ブログ・ポータルサイト | 65〜90% |
業界別直帰率
以下は、業界別のWebサイトの直帰率をまとめた表です。各業界の特性により直帰率が異なり、ユーザーの目的や行動パターンが影響を与えています。
| 業界 | 平均直帰率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 飲食 | 65.5% | 店舗情報やメニューを確認後、目的を達成して離脱する傾向が強い。 |
| 科学 | 62.2% | 専門的な情報を検索し、必要な内容のみ閲覧するため直帰率が高め。 |
| ニュース | 56.5% | 記事単位で閲覧されることが多く、1ページで完結するケースが多い。 |
| エンターテインメント | 56.0% | 映画や音楽など特定の情報を得るために訪問し、他ページへの遷移が少ない。 |
| 美容・フィットネス | 55.7% | 製品やサービス内容を確認し、必要な情報だけで離脱するケースが多い。 |
| コンピューター・電子機器 | 55.5% | 製品仕様確認や比較が主目的であり、短時間で必要な情報を取得する傾向がある。 |
| 自動車・乗り物 | 51.9% | 購入検討者が製品情報を深く調べるため、回遊率が比較的高い。 |
| ファイナンス | 51.7% | サービス内容や料金プランを確認後に離脱するケースが一般的。 |
| 旅行 | 50.6% | 複数のプランやオプションを比較するため、回遊率が高め。 |
| ビジネス・産業 | 50.5% | 業務関連のサービスや製品情報を調べるために利用されることが多い。 |
| 不動産 | 44.5% | 高額商品のため、詳細情報を複数ページで確認する傾向が強く直帰率は低め。 |
一方、低直帰率の業界としては、不動産やECサイトなどが代表的です。これらは、高額商品や購入検討段階で複数ページを閲覧するため直帰率が低めです。
これらのデータは、自社サイトの直帰率改善に役立つ参考基準となります。同業界内で比較しながら適切な施策を講じることが重要です。
直帰率が高い主な原因4つ

直帰率を改善するポイントは訪問者が直帰する理由を知ることです。そこで、今回はよくある直帰率の原因を4つご紹介します。
原因1.ユーザーのニーズに合っていない
訪問者が求めている情報とページの内容がマッチしていないと訪問者は短い滞在時間ですぐに閲覧を中断します。
コンテンツのタイトルや見出しが内容とずれていないか確認し、必要であれば修正をする必要があります。
例えば「卵料理 簡単」というワードで検索した最初のページに工程数の多い凝ったレシピが掲載されていたらユーザーはすぐに他のページに移ってしまいます。
このように、ページがユーザーのニーズに応えれていない場合、直帰率は高くなります。
原因2.Webサイトの導線が分かりづらい
最後まで読み終えても次のページのリンクが表示されていなかったり、デザインにこだわりすぎてリンクが分かりづらいと訪問者は次のページへ移動することを諦めてサイトを離脱してしまいます。
また、「〇〇の方はこちら」などユーザーごとのコンバージョンに繋がる工夫を行いましょう。ユーザー心理に基づいたサイト作りを行うことで直帰率は低くなる傾向にあります。
ページへの内部リンクを目立つように作成し、適切なコンテンツへのリンクを張るなどの対策を行いユーザーの直帰を防ぎましょう。
原因3.Webサイトの読み込みスピードが遅い
ユーザーは様々な環境でサイトを観覧します。環境の変化がある場合でも、ページの読み込み速度が遅いと全て表示される前に直帰してしまう可能性があるため注意しましょう。
近年は移動中にスマホでサイトにアクセスするユーザーも増えているため、読み込みスピードが遅いことはサイト運用にとって致命的です。
ユーザーは手軽に目的を達成したいと思っているため少しの時間もストレスに感じてしまいます。サイトのページ移動の読み込みスピードの改善は直接的な直帰率改善となるでしょう。
原因4.ユーザーの目的が解決され満足して離脱する
ブログやニュース記事、広告型のランディングページなどページ自体で目的が達成されるものであれば、直帰率が高くても問題視する必要はありません。
何かの検索ワードの場合も1ページ内の情報が多く、そのページだけで訪問者が求める情報が十分に得られるようになっているとユーザーは読み終えた時点で満足して直帰します。
ユーザーにとっては良いコンテンツでも大半のサイトではコンバージョンに繋がらないと運営側にとっては成果に繋がりません。
平均滞在時間が長くても直帰率が高い場合はこのケースで当てはまる可能性が高いので、見直してみましょう。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
直帰率の改善方法5選

直帰率が上がる理由は様々あるように改善方法も様々あります。本記事では改善方法を5つご紹介します。実際に自社サイトを改善する際の参考にして下さい。
1.ページ内容とキーワードの見直し
訪問者の検索ワードを分析してニーズを予想し、ユーザーの期待に応えられるような情報を追加するなどしてコンテンツの充実化を図り直帰率を改善しましょう。
検索行動でユーザーニーズに合わないサイトの表示は直帰率を高めてしまいます。
タイトルやディスクリプションの見直しを定期的に行い、ページの内容を変更するニーズにマッチさせていけば直帰率が改善されます。
2.導線の見直し
サイト流入の導線やデザインを見直しを行うことで、より読みやすい設計にすることも直帰率改善には効果的です。
また、ランディングページなどで見られるCTAボタンの配置には注意が必要です。
ユーザーが求めているページへの導線が複雑な場合や、誘導するデザインが認識しにくい場合はページから離れる原因になります。
CTAの配置の見直しや、スムーズな導線の確保で直帰率は改善されるでしょう。
3.クリエイティブの見直し
ユーザーがサイトのコンテンツで満足した場合も、見やすい登録ボタンやお問合せフォームがあれば、訪問者の行動を次のステップへと促すことが可能です。
流入の多いページでは、見やすさを重視した施策を取り入れることで直帰率の改善だけではなく見込み客の獲得へと繋げることも可能になります。
デザインは一目で読みやすくすることが重要です。文字ばかりのコンテンツではなく、画像や動画、表などを適宜挿入しユーザーの目を惹く工夫が必要です。
WEBサイトを読みやすいデザインにする方法
要所に画像や動画を挿入する
表や箇条書きを用いる
2〜3行ごとに改行する(逆に改行ばかりの場合は文章をまとめる)
情報を分する
文字を敷き詰めすぎず、余白を作る
4.表示速度の改善
魅力的なビジュアルはユーザーの興味を引くのに効果的ですが、クオリティにこだわるあまり画像など入れすぎるとサイトが重くなり表示速度が遅くなり直帰率に繋がります。
ページ表示速度を改善する前に、WEBサイトの表示速度を確認しましょう。ページ速度を知るにはGoogleが提供しているPage speed insightsがおすすめです。
5.内部リンクを貼る
ページ内容が充実しており、ユーザーのニーズを満たすものであればそのページで全てが解決してしまうため、直帰率が高くなります。
実際に企業側が期待するアクションや提供したい情報が閲覧ページの先にある場合、あまり意味がありません。このような場合、内部リンクを貼ることで直帰率を下げることができます。
ユーザーやニーズや興味を分析し、適切な内部リンクを貼ることで本来到達してほしい情報へと誘導していきましょう。
▼下記の資料はヒアリングを効率化できるヒアリングシートの作り方をステップ別に解説した資料です。ぜひご活用ください。
直帰率が低すぎる場合の見直すべき3項目

直帰率はページの特性や構造によって上下することはありますが、想定の数値との乖離が大きすぎる時は設定ミスの可能性があります。
設定を間違っていても、どの部分が間違っているかを理解しない限りは正しい直帰率は算出できません。
直帰率の設定が間違っている時の3つのパターンをご紹介します。
1.トラッキングコードの設定ミス
トラッキングコードとはGoogleアナリティクスが提供するサイト計測用のプログラムのことです。
計測はサイト内のページが読み込まれると共に実行されユーザーの流入先や検索キーワード、行動履歴やページ滞在時間などのデータを収集します。
極端に直帰率が高い場合、このトラッキングコードが複数挿入されてることがあります。トラッキングコードが複数挿入されると1ページに対して複数のページビューが同時にカウントされてしまう恐れがあります。
複数のトラッキングコード挿入はいくつかの要因がありますが、正しく直帰率を算出するためには余分なコードを削除するなどの対応が必要です。
2.イベントトラッキングを計測してしまっている
直帰率が低すぎる原因としてもう一つ考えられるのがイベントトラッキングが設定されていることです。
イベントトラッキングとはGoogleアナリティクス内での行動を追跡するための機能です。設定することでリンクボタンが何回押されたか、記事を完読したユーザーはどのくらいか、それぞれの行動がおきた順番など、Googleアナリティクスだけでは把握できない数値を確認できるようになります。
3.どちらの項目も当てはまらない場合
上記2つの原因に当てはまらないとしても、数値が極端に低い場合であれば他の不具合が潜んでいることを疑いましょう。
基本的にどのページであっても直帰率が一桁台になることは考え難いです。直帰率が低すぎる場合はヘルプページなどGoogleアナリティクスに直接質問して原因を突き止めましょう。
▼Interviewz(インタビューズ)では、ヒアリング体験をDX化し、質の高い情報をスピーディーに収集、顧客・ユーザー理解を深め、サービスのあらゆるKPIの改善を可能にします。
テキストタイピングを最小化した簡単かつわかりやすいUI/UXと、収集した声をノーコードで様々なシステムに連携し、ユーザーの声を様々なビジネスプロセスで活用することで、よりビジネスを加速させることが可能です。
以下の資料ではそんなInterviewz(インタビューズ)のより詳しいサービスの概要を3分で理解いただけます。Interviewzについてより詳しく知りたい方は、以下の資料をご参照ください。
直帰率の改善にはインタビューズのヒアリングツールがおすすめ!
インタビューズのヒアリングツールは、直帰率改善に効果的です。このツールを使用することで、ユーザーのニーズや課題を正確に把握し、サイトコンテンツの最適化が可能になります。
また、効率的なヒアリングプロセスにより、時間とコストを削減しつつ、質の高い情報を収集できます。さらに、ユーザーの行動データを蓄積し分析することで、継続的な改善が可能にです。
結果として、ユーザーエクスペリエンスが向上し、直帰率の低下とコンバージョン率の向上につながります。
そこで、ぜひこの機会に、インタビューズ「ヒアリングツール」の30日間の無料トライアルをお試しください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。